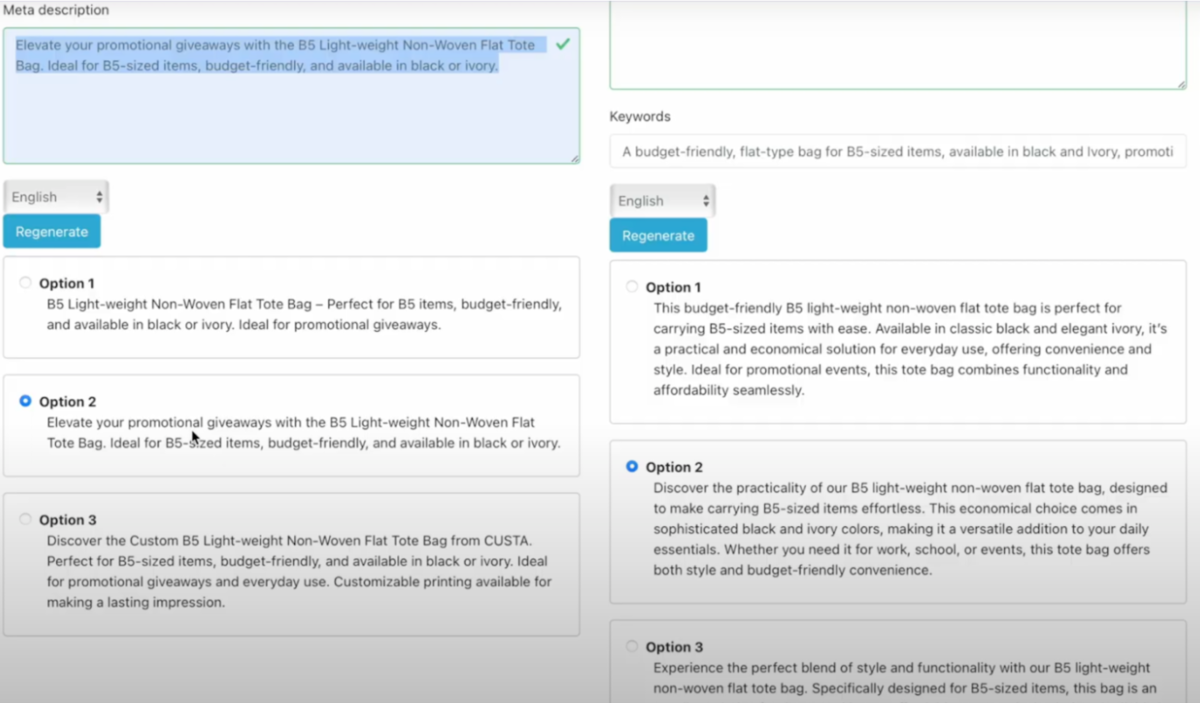はじめに
ラクスル株式会社の課題解決型インターンに参加させていただいた上田です。このブログでは、インターンでの活動内容や学び、感想をまとめています。参考にしていただければと思います!
インターン概要
内容:ラクスルのサービスにおいて実際に抱える課題に挑戦(4~5人チームで開発に取り組みます)
期間:2024/09/09(月) ~ 09/13(金) の5日間
時間:11:00 ~ 19:00(開始時間が遅めで、朝が弱い私にとっては嬉しかったです!)
形式:2日間オンライン、3日間対面のハイブリット形式(私は中部地方に住んでいるため、2日目の夜に東京へ移動しました)
待遇:100,000円/5日間、交通費・宿泊費支給(交通費や宿泊費だけでなく、給与まで出るのはとてもありがたかったです!)
場所:目黒駅から徒歩5分(開放的で緑がたくさんあり、素敵な空間でした!)
※ 募集ページ

なぜ参加したか
- 実務に携われる点に魅力を感じた
- 開発経験を積みたかった
- ラクスルの職場の雰囲気や社員の方々の人柄を知りたかった
取り組み内容
テーマ:注文データから顧客ロイヤルティを可視化するプロジェクト
具体的には、「顧客の注文データをもとにロイヤルティを分析し、特定の顧客層に対する効果的なリテンション施策を提案するためのツール」の開発を行いました。
ラクスルのエンタープライズ事業部では、お客様にラクスルをより便利に使っていただくために日々活動しています。しかし、現在は多くのデータを収集しているものの、それらを十分に分析し、活用するに至っていません。今回は蓄積された各種データから、より効果的にラクスルをご利用いただくための提案に役立つ、ビジネスメンバーをラクにするツールの開発をテーマに取り組みました。
チームは、インターン生4名とメンター4名の構成で、実質的な開発期間は約3. 5日間でした。インターン生で議論・開発を進めながら、何かあればメンターに相談させていただくという形で進めていきました。
実際のデータを扱い、ビジネスメンバーへのヒアリングも実施する時間を設けていただき、実務に近い形で一連の流れを体験できたことは非常に貴重な経験となりました。
5日間のスケジュール
1日目:オンライン
- 開会式
- チームメンバーとの顔合わせとチームビルディング
- 開発環境の設定などを含むチーム開発
- 一日の振り返り
オンラインでの初日は、開会式を経て、チームメンバーと顔合わせとチームビルディングが行われました。メンターも参加し、自己紹介とワーキングアグリーメントを設定しました。その後、開発環境の設定などを行い、チーム開発がスタート。最後に、日々の進行について振り返りを行いました。
2日目:オンライン
- ほぼ一日を通してチーム開発
- 一日の振り返り
- 東京への移動(宿泊が必要な参加者のみ)
2日目は、開発に集中し、移動も含めて18時までの活動でした。午後は開発に専念し、夜には東京へ移動しました(宿泊が必要な方のみ)。
3日目:対面
- オリエンテーション(自己紹介、社内見学)
- チームメンバーとランチ
- 午後から開発
- 3 on 1面談
- 一日の振り返り
- 懇親会
3日目は、オリエンテーションで自己紹介とオフィスを見学しました。全体的にとにかく開放的で、のびのびと働けそうだと感じました。昇降デスクによる立ち作業エリアやガラス張りの会議室、ソファや個室など、さまざまな働き方ができそうな空間で、とても魅力的でした。
昼食時にはメンターやチームメンバーと初対面し、弁当を食べながら交流を深めました。その後、午後からは開発に取り組む時間となり、チーム全員で集中して作業を行いました。
また、個別に行われた「3 on 1面談」では、メンターと約30分間お話しする機会がありました。メンターは非常に温かく、気軽に質問をすることができ、貴重なフィードバックを得ることができました。
そして、1日の振り返りを経て、夜は懇親会が開催されました。社員の方々とローテーションしながらお話しする機会があり、チームメンバー以外のインターン生とも交流することができ、とても楽しい時間を過ごしました。
4日目:対面
- チーム開発
- 新卒入社の先輩とのランチ
- 再度チーム開発
- 一日の振り返り
4日目は、ほとんどの時間をチーム開発に費やしました。また、2024年入社の新卒社員とピザランチを共にし、近い年齢の社員と気軽に話す機会がありました。その後も開発を続け、日々の進捗を振り返りました。
5日目:対面
- チーム開発(午前まで)
- お疲れ様ランチ(お寿司)
- 成果発表会
- お客様へのプレゼン
- 個人振り返り、閉会式
最終日は、午後の成果発表会に向けて、午前中は開発に集中して取り組みました。資料の提出期限が迫っていたため、集中して作業を進めました。お昼には「お疲れ様チームランチ」があり、各チームにお寿司が提供されました!発表前の忙しさもあって、資料を作成しながら食事をしましたが、美味しいお寿司で少しリフレッシュできました。
午後からは「成果発表会」が行われ、各チームが3分間で成果物を発表しました。他のチームの内容に触れることがなかったため、さまざまな成果物を見てとても面白かったです。また、発表のクオリティの高さもさることながら、特に英語で発表しているチームには驚かされました!
その後、実際にビジネスメンバー向けに成果物を直接プレゼンテーションしました。とても良い反応をいただき、作りっぱなしではなく、実際に使用する方に見てもらうことで、達成感ややりがいを実感することができました。
最後に「個人振り返り」と「閉会式」が行われ、インターン生一人ひとりが振り返りを行い、それに対してメンターがフィードバックをくださいました。自分へのフィードバックはもちろん、他の人へのフィードバックを聞くことも新鮮で、その中から得られる学びも多く、とても貴重な時間でした。
学んだこと
技術面
私は開発経験が豊富なわけではなく、技術面で不安を抱えていましたが、メンターやチームメンバーが非常に優しく、何でも気軽に相談できる環境が整っていたおかげで、しっかりと学びながら課題に取り組むことができました。その結果、BigQueryやStreamlitについて深く理解でき、担当した役割を果たせたことに大変満足しています。メンターやチームメンバーには心から感謝しています。
タイムマネジメント面
5日間という限られた期間でプロダクトを完成させるという点が難しかったですが、その中で開発期間やチームの技術力を考慮しつつ、スケジュールを立てて進める力がついたのではないかと感じています。(発表資料はギリギリになってしまいましたが…何とか形になって良かったです!)
働くイメージ
今回は実際のデータを使い、ヒアリングも複数回行いながらプロダクト開発に取り組みました。設計書を作成することはありませんでしたが、それでも非常に実務に近い形で開発の一連の流れを体験できたと感じています。利用する側のニーズや課題を引き出し、最終的にソリューションを提案する一連のプロセスを体験する中で、エンジニアとしてラクスルで働くイメージが鮮明になりました。そういった観点でも、大変貴重な経験をさせていただけたと感じています!
個人的に「良い」と感じたポイント
手厚いサポート
メンターがインターン生とほぼ同数ついてくださり、常に見守ってくださっていました。困ったときにはすぐに対応してくださり、大変助かりました。技術的なことから議論の進め方まで幅広くサポートいただきました。特に、若手社員からCTOまで、さまざまな立場の社員の方々がメンターとして関わってくださり、さまざまな視点からのアドバイスをいただけたことは非常に有意義でした。
ビジネスメンバーへのヒアリング
実際にプロダクトを利用する側に直接ヒアリングする機会があり、生の声を聞くことで得られるアイデアや欲しい機能が明確になり、開発の方向性を決める重要なプロセスとなりました。また、この経験が実際の業務におけるニーズ把握に役立つことを実感しました。
プロダクトの稼働イメージ
最終日には、実際に作成したプロダクトを社員にプレゼンする機会があり、「すごい!」「使いたい!」というフィードバックをいただけたことが大変嬉しく、やりがいを感じました。自分たちが作ったものが実際に利用される喜びや達成感を感じることができました。
待遇と責任感
この5日間は、交通費と宿泊費が支給され、さらに報酬もいただきました。忙しい時期にこれだけ手厚い待遇をしていただけたことは非常にありがたく感じています。また、報酬を得ることで「働いている」という実感と責任感を持ちながらインターンシップに取り組むことができました。(強制ではなく、個人的な感想です)
会社の雰囲気
ラクスルのオフィスは開放的で、緑がたくさんあり、とても広々とした空間でした。また、社員同士の仲が良く、部活動など業務外でもさまざまな活動をしている方が多いことが私的に非常に魅力的なポイントでした。私自身が5日間を通して楽しかったと思えたのも、社員の方々やチームメンバーの雰囲気が良かったおかげだと思っています!
おわりに
全体を通しての感想は「楽しかった!」です。開発経験が少ない中での参加でしたが、社員の方々やメンバーが非常に温かく、優しい方々ばかりで、初日から不安はすぐに解消されました。気軽に質問できる環境で、のびのびと開発に取り組むことができました。
技術面で不安を感じている方も、ぜひ参加してみてください!楽しく、数多くの学びを得られる貴重な5日間になること間違いなしです!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!